この前はコンプレッサーに関する投稿がありました。勉強になりますね。コンプレッサーは古くからある成熟した技術ですが、細かいところに特許が使われています。今回は特許について少しお話ししましょう。
特許って素晴らしい発明なんだろうな、と思いますよね。実はそうでもないんです。簡単に言えば、「過去にない発明を権利化したもの」です。その発明の内容が素晴らしいかどうかはあまり関係ありません。
特許は国から与えられる権利です。日本の場合は経済産業省の中の特許庁が担当官庁です。早口言葉に「東京都特許許可局」なんてのがありましたが、これは実在しない役所です。あくまでも国の管理です。
今回は特許を取得するための手続きについてお話しします。と言っても特許は非常に複雑なものですので、小生が知っている簡単な範囲のみになりますことをまずお断りさせていただきます。
特許を取得するためには、まず出願しなくてはなりません。一般的には弁理士資格のある人に専門用語で書いてもらいます。出願時に簡単な検査(書式、公序良俗に反しないかどうか等)があり、受理されると出願特許と呼ばれ、「特願XXXXXX」という連番が発行されます。特許庁の統計によると、昨年1年間の出願数は31万8千件以上です。月平均で26千件以上も出願されています。出願特許は、「特許」という名前が付いていますが、特許ではありません。
出願特許は18か月経過すると自動的に公開されます。これを公開特許と呼び、出願番号とは別の「特開XXXXXX」という番号が与えられ、公開広報に掲載されます。広報は特許庁に行かなくても、インターネットで検索することが可能です。公開されてもまだ特許にはなっていません。
公開されるということは、同様の技術を開発しようとしている人や法人に対してプレッシャーになります。これは世界のほとんどの国が採用している「先願主義」という考え方に基づくものです。つまり先に出願した人が保護されるという考え方です。先願主義に対抗する考え方は「先発明主義」と呼び、アメリカはかつてこの考え方でしたが、最近先願主義に変更されたようです。
出願・公開された特許を権利化するためには、内容を審査してもらう必要があります。審査請求できるのは、出願日から3年以内です。何としても権利化したい人や法人は、3年以内に所定の納付金を支払い、審査請求を行います。審査請求して、特許審査官が初めて内容を審査します。昨年1年間の審査請求件数は24万件に及びます。審査官の人数は約2千人ですから、一人で大変な件数を抱えています。
審査はどのように行われるのか。出願された特許を審査するということは、試作品でも作って評価するのかなと思いがちですが、残念ながら全く違います。審査は、過去の出願や登録された特許に類似のものがないかどうか、公知公用の技術から容易に考えられるものでないかどうか、というような視点で行われるのです。国内だけでなく国際的な検索を行います。類似のものが見当たらなかったり、公知公用技術ではない新しい発明と認定されれば、特許査定となります。査定書には「拒絶理由を発見しないから特許査定する」と書かれています。つまり否定すべき理由が見当たらなかったというのが特許査定の根本なのです。
審査請求しても1回の審査で特許査定されることはほとんどなく、通常は過去の類似出願等が列記されて「拒絶査定」されます。拒絶に対して、修正を加えて再審査請求することも可能で、その結果「特許査定」になることもあれば、再度拒絶されることもあります。拒絶を受け入れれば、権利化を放棄することになります。また出願から3年以内に審査請求しなかった場合も自動的に放棄になります。放棄された出願は、公知の技術として、誰でも使うことが可能になります。
特許査定を受け、所定の納付金を支払うと「登録特許」となり、最長で出願日から20年間維持することができます。この期間内は、同様技術を第三者が使うことはできず、使ってしまった場合は特許権利者から損害賠償を請求されることになります。公報で公開されているので「知らなかった」では通じません。
誇らしげに書くことではないですが、小生も特許をひとつ持っていました(既に維持放棄)。お恥ずかしながら特許公報の1ページ目を掲載します。
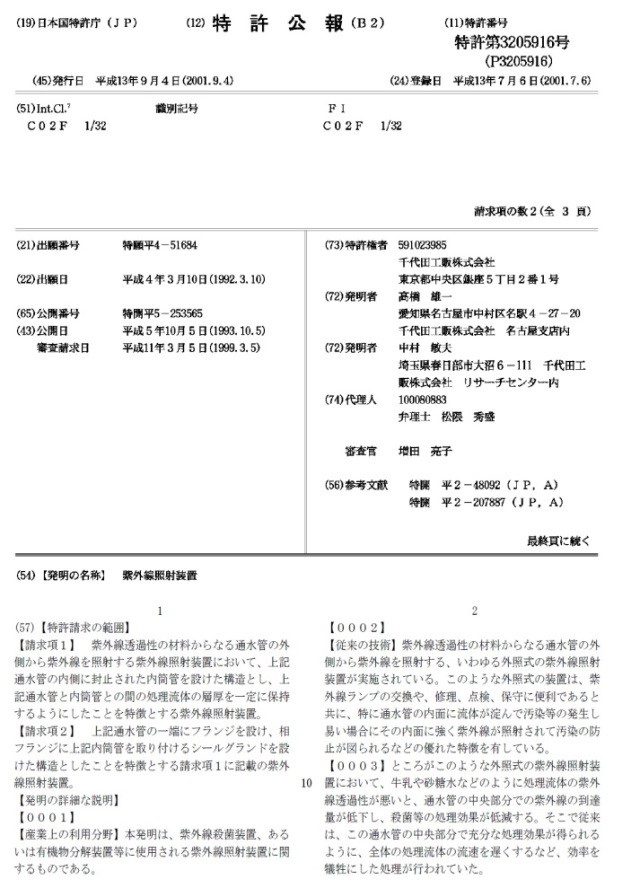
次回は特許戦略について少しお話ししましょう。
