前回、「次回は特許戦略について」と予告しました。非常に奥が深いテーマですので、ほんの概略だけになりますがお読み下さい。
特許は、発明者の権利を国が付与するものです。
当然ながら、特許には利益が発生するので、その利益を守ってもらう仕組みです。
権利を取得するための手続きについては前回お話ししましたが、実際に特許を取得するためにどれぐらいの費用がかかるのでしょう?
特許は、知識があれば個人でも出願可能ですが、通常は弁理士事務所を通じて出願します。
弁理士は、個人が考えた技術を要領よく、しかも要点をまとめ上げた文章にして特許庁に出願してくれます。
出願のボリューム(請求項という項目の数)にもよりますが、特許庁への出願費用以外に弁理士事務所への手数料も必要で、合計すると1件あたり25~30万円ほどかかります。
また権利化するためには特許庁に審査請求しなければなりませんが、この時に12~15万円程度かかります。
晴れて登録特許になると、成功報酬として弁理士事務所に10万円程支払わねばなりません。
登録されるまで合計で約50万円は必要です。そして登録された特許を維持するためにも費用がかかります。
仮に特許を20年間維持したいとすると、維持のためだけで150万円程度かかります(1年ごとの費用は年数が過ぎるほど高くなります)。
出願から維持まで、合計すると200万円にもなります。
高額の出費をしてまで特許を取得するのは、それによって利益を得たいからです。
簡単に言えば、その技術によって製造される商品を自社だけに限定し、市場において優位に立ちたいからです。
競合する他社は、同様の技術を使用することができないので、特許に抵触しない他の方法を開発しなければなりません。
市場に遅れを取るだけでなく、開発費用も余分にかかることになります。
誰しも市場で優位に立ちたいと考えて特許を出願するものですが、審査請求しなかった場合でも、出願時から3年間は審査請求可能期間として、他社を牽制することが可能で、これも戦略と言えます。
したがって、出願せずに他社に先を越されてしまうことを考えれば、出願する意義は大きいと言えます。
世の中には特許マニアと呼ばれる人もいます。でも彼らの多くは、どこかの企業がその特許に目を付けて商品化してくれることを待ち望んでいます。
個人が特許権利を企業に売るという戦略です。
自社で開発した技術を用いて、特許出願せずに商品化することもあるでしょう。
ところが同様の技術を他社が特許出願していることに気付いたら大変なことになり兼ねません。
他社が先に権利化してしまったら、自社は特許侵害として損害賠償を請求されるかも知れません。
こういった事態を防止するため、開発経緯はできるだけ詳細に記録しておくべきです。
裁判になった時、記録が証拠として認められれば、他社の特許を無効化することも可能になるかも知れません。
高額な費用を払ってまで権利化した特許を、費用対効果の観点から検討することも必要になります。
前回の投稿で、小生が発明した特許があると書きましたが、実はそれは商品化されておらず、特許によって得た利益は全くありませんでした。
身近な特許を紹介して、特許の稿を閉じたいと思います。
お口の恋人L社の冷菓である「雪見だいふく」は特許です。

この特許は既に権利期間を経過していますが、少し範囲を変えて、実質的に特許を継続しているようです。
今ではお目にかからなくなりましたが、フロッピーディスクはドクター中松氏の特許として有名でしたね。
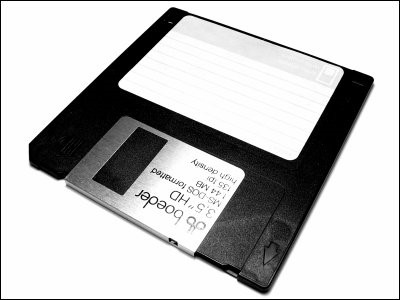
そうそう、特許だけじゃなく、商標、著作物なども特許と同様に権利化されています。
C社の腕時計G-SHOCKはご存知ですね。
C社は、G以外に、A、B、C…Zまで全ての商品名を世界各国で商標登録し、類似品が販売されないよう手を打っていたらしいです。
皆さん、何かいいアイデアがあれば、是非とも権利化してみて下さい。一攫千金も夢じゃないかも。
